OMSとは?EC・小売業向け注文管理システムの機能と導入メリットを解説
ECサイトや実店舗の注文管理に課題を感じていませんか?
複数の販売チャネルを運営していると、注文処理や在庫管理が煩雑になり手作業の負担が増えがちです。「受注ミスを減らしたい」「在庫のズレをなくしたい」「業務をもっと効率化したい」とお考えなら、OMS(注文管理システム)の導入をおすすめします。
本記事ではOMSの基本機能から導入メリット、選び方のポイント、具体的な活用方法まで分かりやすく解説します。
目次
OMSとは
OMSとはOrder Management Systemの略称で注文(受注)管理システムと呼ばれ、商品の受注から出荷までを一括で管理するシステムのことです。
複数のECサイトを運営している企業や、ECサイトの他に実店舗もあるといった企業にも注文を一か所にまとめることができるシステムとして活用されています。
OMSを活用することで、ECと実店舗にまたがる複数店舗を運営していても、注文情報を一元管理でき、業務効率化につながります。また、リアルタイムにデータを更新できるため、販売機会のロスも低減することができます。
OMSとよく比較されるのがWMS(Warehouse Management System)です。WMSは在庫管理や入出庫管理を行う倉庫管理に特化したシステムを指します。
| OMS / 機能 | 内容 | 導入によるメリット |
|---|---|---|
| 受注管理 | ECサイト・実店舗の注文を一元管理 | 手作業を削減し、受注ミスを防ぐ |
| 在庫管理 | 販売チャネルごとの在庫をリアルタイム同期 | 在庫切れや過剰在庫を防ぎ、販売機会を最大化 |
| 出荷管理 | 出荷指示・配送業者との連携・納品書発行 | 出荷スピードの向上とヒューマンエラーの削減 |
| 顧客管理 | 購入履歴・リピート率などのデータ管理 | CRM(顧客関係管理)と連携して、リピート購入・アップセルを促進 |
| 決済・請求管理 | 会計システムとの連携・入金確認の自動化 | キャッシュフローの管理をスムーズに処理 |
注文管理の流れ6ステップ
.gif?w=1120&h=630)
OMSの詳細をお伝えする前に、注文管理の流れをおさらいしておきましょう。
注文管理は、大きく以下の6つのステップで進みます。
1.注文受付
個客からの注文が入れば、それを受け付けます。
ECの場合は、発送のために必要な住所などの情報が不足していないか、この段階でチェックします。
2.発送依頼
ECの場合、受け付けた注文内容で発送の依頼を行います。
実店舗の場合は、このステップは飛ばします。
3.出荷準備
発送依頼を受け、梱包など出荷の準備を行います。
4.請求管理
顧客へ送付する請求書を発行します。
5.仕入管理
注文を受けて出荷した数量に合わせて仕入を行い、在庫量をキープします。
6.在庫管理
帳簿上の数量と実際の在庫数を照らし合わせる棚卸や、適正な在庫量を保つための管理を行います。
OMSの重要性・導入すべき理由
注文管理の機能は、POSや販売管理システムなどにも搭載されています。それが、なぜ独立したシステムとして必要なのでしょうか?
その理由は、販売業務を取り巻く環境の変化にあります。インターネットの普及や通信速度の高速化に伴い、さまざまなサービスの登場とともにECサイトも増加しました。さらに、新型コロナウイルスの感染拡大が非接触で買い物ができるECを加速させました。
これに伴い、独自ECサイトに加え、複数のECショッピングモールへの展開など、オンラインショップの店舗数を増やす企業も出てきました。複数のオンラインショップを運営することになれば、注文管理も煩雑化します。
そこで、注文管理に特化したOMSで注文情報を一元管理し、業務を効率化する必要が出てきたのです。
OMSの主な機能|受注・出荷・在庫を一元管理
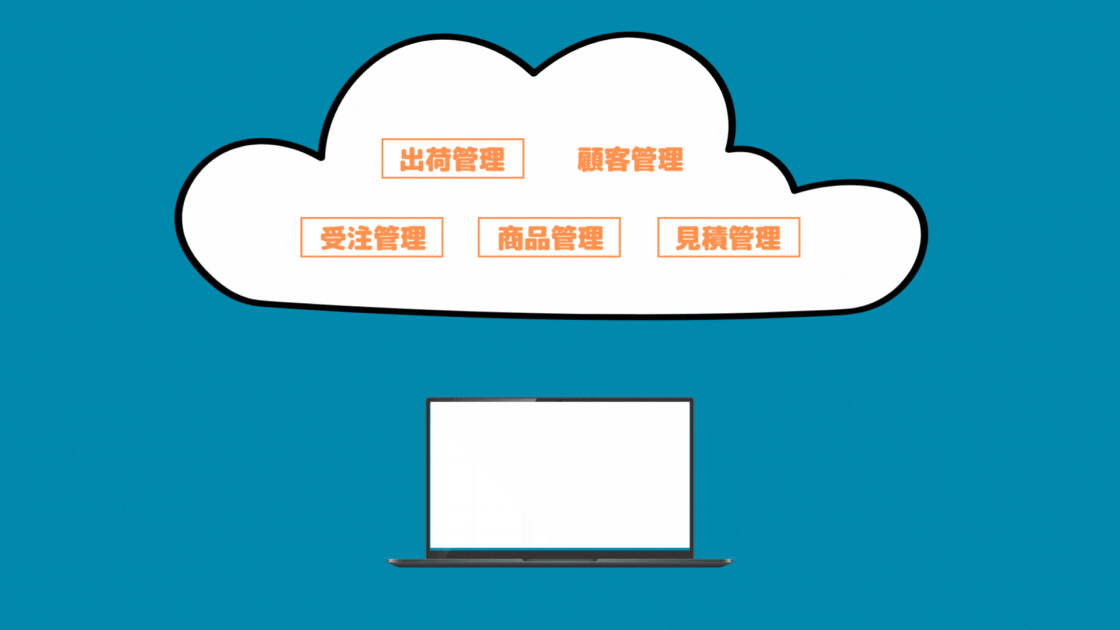
OMSにはどのような機能が含まれるのか確認していきましょう。
受注管理
受注管理とは、顧客から入った注文を処理する機能です。ECサイトの場合はショッピングカートと連携して在庫管理につなげます。ECサイトであれば注文と同時にお礼メールを自動送信する機能などもここに含まれます。
会計システムとの連携も可能です。
出荷管理
出荷管理とは、注文に応じた商品の出荷を指示する機能です。
商品を無事にお届けするまでの業務になり、納品書や売上伝票の作成機能が含まれます。他にもピッキングや梱包、配送方法についての指示が含まれる場合もあります。
商品管理
在庫管理を含む商品管理はECサイトを運営する上で重要な業務です。
在庫過多や在庫不足を防いで適正量を保つことで売上を最大化します。このような在庫適正量の計算も自動で行うのがOMSシステムの特徴ともいえます。
また、倉庫管理と連携させて物流自体を一括管理できるOMSも増えています。
顧客管理
顧客情報を記録して保存しておくだけでは十分な顧客管理とは言えません。データを活用して初めて適切な顧客管理が行われていると言えるでしょう。
OMSはこれらの顧客データを分析してマーケティングに活用できる機能が含まれます。
見積管理
卸売やBtoBの場合は注文をいただく前に見積書の作成が必要なケースもあります。
OMSには見積書作成機能が含まれるため、過去の内容を参照することも可能です。
入金送金管理
ECサイトではネット上で金銭のやり取りが行われるため、正しく入金がされたのかまで細かく管理しなければなりません。
従来会計管理を担っていた会計ソフトや金融機関と連携できる機能がついている場合もあれば、OMS自体に会計管理が含まれることもあります。
OMSを導入するメリット
OMSを導入するメリットについてご紹介します。
業務効率がアップ
エクセルなどは複数チャネルの注文管理が非常に大変です。
OMSを導入するとまとめて管理ができるため、手動で注文管理を行っていた時と比較して人為的ミスなどが減らせることが大きなメリットの1つです。
また、OMSなら様々な業務が自動で行われるため時間短縮となる上に人的費用を削減することにもつながります。
発注管理に必要な伝票や書類の多くがメールなどの電子形式でやり取りされることになり、紙に印刷するためのコストも削減できます。
販売機会を逃さず出荷ができる
手動で注文管理を行っている場合には、前の作業が完了するのを待ってから次の作業を行うのが一般的です。マニュアルで管理していた場合、時間差が大きいことや予測精度が低いこともあり、せっかく注文をいただいたのに在庫切れという事態も発生してしまうことがあります。
一方、OMSなら注文が確定すると同時に在庫の確認と出荷指示ができてしまうため顧客を待たせる時間が少なくなります。またOMSは適切な在庫量を予測することで常に在庫を切らすことなく循環させることができ、販売の機会を逃さず出荷することができます。
OMSの導入デメリット
OMSを導入するにはメリットばかりではなく、デメリットも理解して検討する必要があります。
コストがかかる
これまで無料ソフトやエクセルで注文管理を行っていた企業であれば、OMS導入の費用は大きく感じることでしょう。
また現状の運用方法から移行する必要があるため、人的コストもかかります。
導入する際は期待できる効果と発生するコストを十分に比較し、検討する必要があります。
業務フローの見直しが必要
これまで行ってきた注文管理業務の順番が変わることにより、中には人の手を必要としなくなるケースも出てきます。
そのためOMS導入に向けた業務フローの根本的な見直しが必要です。
OMSを選ぶ3つのポイント|システム比較で失敗しない方法
OMSを選ぶ際には以下の3点に注意する必要があります。
操作性や運用方法
どんなOMSでも、スタッフが操作できずに使えないとせっかくの費用が無駄になってしまいます。
お試し期間でどのような操作画面なのか確認できるとベストです。
特に、それまでにあまりシステムを導入してこなかった企業や、従業員のITリテラシーが低いという店舗などでは、シンプルな画面で直感的に操作でき、操作ミスが起きにくいOMSを選ぶことが大切です。
さらに、お試し期間でどのような操作画面なのか確認できるとベストです。
OMSの運用方法にも注意が必要です。
すでに何らかのシステムを導入・活用している場合は、注文情報(データ)を連携できると、さまざまな業務の効率化につながります。既存システムと連携できるものを選びましょう。
また、OMSは提供形態としてクラウド型とオンプレミス型があり、以下のような特徴があります。
オンプレミス型は社内のパソコンに直接インストールして使うタイプとなり、OMSがインストールされた端末からのみ利用することができます。
クラウド型はネット環境が整っている場所であればどこからでもオンラインで利用できるため、端末が限定されないことからもリモートワークでも活用できます。
自社の要件を満たす方を選択しましょう。
サポート体制や保守機能
OMS導入時はもちろんですが、使用中に操作に不明や不具合など出てきた場合に問い合わせられるサポート窓口があるかどうかも重要なポイントです。
受付時間や対応の方法(対面、Web会議システム、チャット、メール)なども確認しておきましょう。
場合によってはサポートが別料金ということもあるため、必要に応じたサポートが受けられるものを選びましょう。
また、使っていくうちに設定を変更したり、新たな機能が必要になったりすることも少なくありません。機能拡張が可能だったり無償でアップデートできたりなど柔軟に対応できるタイプを選ぶことで、長期的に利活用できるでしょう。
セキュリティ対策が行われる範囲についてもよく確認しておく必要があります。
他システムやチャネルとの連携
オンラインショップ運営の場合は特に、複数の販売チャネルと連携できるかどうかが最大のポイントです。
仮に現在は自社サイトのみだったりECサイトが1つしか無いという場合でも、今後規模が大きくなったときに連携できるチャネルが限られてしまうとOMSを変更せざるを得なくなります。
OMSは出入金など会計管理と連携させることで大きな効果を発揮できるため、会計はもちろんのこと、自社内のあらゆる業務と連携できるかどうかも見極める必要があります。
Shopifyと連携できるおすすめOMS
他システムとの連携の中でも、特に近年、急速にシェアを伸ばしている、カナダ発のECサイト制作プラットフォーム「Shopify(ショッピファイ)」と連携できるOMSの中から、おすすめ5点についてご紹介いたします。
キャムマックス

キャムマックスは、OMSではなく、注文管理の機能を持つ、オムニチャネル対応の中小企業向けERPです。
キャムマックスには、各種ECへのAPI連携が用意されており、Shopifyとも連携可能です。
EC側から受注データの連携、EC側への出荷完了データや在庫データをキャムマックス側へ連携でき、キャムマックスで受注から出荷までの一連の業務運営・管理が可能です。
Shopifyのほかに、メイクショップやショップサーブなどともAPI連携できます。
このAPI連携の利用料金は、自社サイト1店舗まで無料、店舗追加には、導入費用3万円、月額利用料が1万円かかります。
LOGILESS(ロジレス)

LOGILESS(ロジレス)は、ECの受注から出荷までの業務を自動化できるシステムで、OMSとWMSが一体化したものです。
多くのECモールやショッピングカートに対応しており、Shopifyのほか、メイクショップやカラーミーショップ、BASEなどとも連携できます。
利用料金は、基本料金の月額2万円に、従量課金で月間出荷数に応じて出荷単価がかかってきます。ただし、月間500件以下の場合は発生しません。
コマースロボ

コマースロボも、OMSとWMS一体化のEC自動出荷システムで、RPA(Robotic Process Automation)が内蔵されています。RPAによって、受注処理、EC連携、データ変換、同梱処理の4つの業務を自動化できます。
コマースロボでは、Shopify をはじめとするECモールやショッピングカートのほか、宅配システム、後払システムともAPI連携が可能です。
利用料金は、初期費用が無料で、「フリープラン」「自動出荷プラン」「SCMプラン」の3つのプランが用意されており、フリープランは出荷件数が月間100件までなら無料で利用できますが、100件を超えると自動的従量課金がスタートします。自動出荷プランは、基本料金が月額1万円、SCMプランは基本料金が月額3万円に加え、それぞれ、月間受注件数に応じた従量課金制が組み合わされます。
ネクストエンジン

ネクストエンジンは、複数のネットショップの受注・在庫業務を自動化・効率化できる基幹システムです。機能が豊富なことが特長の一つで、200種類以上の機能が搭載されています。
Shopify をはじめとするショッピングカートのほか、倉庫連携システムや会計管理システム、POS連携システムなどとも連携できます。
また、API連携以外にCSVデータによる連携も可能です。
利用料金は、初期費用が無料で、基本料金が月額1万円、月間受注件数に応じて金額が設定された従量課金制が組み合わされます。
mylogi(マイロジ)

mylogi(マイロジ)は、商品管理から受注、出荷、在庫管理、出荷、配送までに対応した、OMSとWMS一体化の物流システムです。EC専業の会社が作ったシステムでECに特化しており、小ロットにも対応しています。
ShopifyをはじめとするECモールやショッピングカートに加え、上でご紹介したネクストエンジンとも連携できます。
利用料金は、初期費用が無料で、月間出荷件数300件までのBasicプランでは月額料金が1万5,000円、301件目からは従量課金制。月間出荷件数1,000件までのプランでは月額料金が3万円、1,001目からは従量課金制となっています。
『キャムマックス』でOMSを上回る管理を実現!多機能システムで業務を最適化

キャムマックスは中小企業向けに開発された基幹業務システムです。
複数のECサイトを持つ企業様にとって必要不可欠な機能が豊富に盛り込まれているのですが、これはOMSの注文管理にとどまりません。
キャムマックスでは、販売管理機能の中で受注情報を共有することができます。オムニチャネルに対応しているため、ECモールや自社ECサイト、実店舗にまたがるデータを一元管理できます。また、注文ステータス管理で作業や処理の状況を瞬時に把握することが可能です。
OMS導入をお考えの企業様はぜひ一度キャムマックスまでご相談ください。
FAQ(よくある質問)
Q1. OMSとは何ですか?どんな企業に必要ですか?
A:OMSとは注文管理システムのことを指します。主に、ECサイトや実店舗で発生する注文を一元管理して、受注処理や出荷、在庫管理をスムーズに行えます。
特に、複数のECモールや自社ECサイトを運営している企業、実店舗とオンラインショップの両方を展開している企業、または注文処理や在庫管理の業務効率化を目指している企業におすすめです。
Q2. OMSを導入すると、どんなメリットがありますか?
A:エクセルなどで手動管理していた注文処理を自動化することで、ヒューマンエラーを削減して処理速度や精度を向上できます。また、在庫状況をリアルタイムで管理できるため、在庫切れによる販売機会の損失を防ぐことができます。
Q3. OMSの導入コストはどれくらいかかりますか?
A:クラウド型の場合、月額数万円程度で利用できるものが多いです。一方、オンプレミス型やカスタマイズが必要なシステムの場合、初期費用が数十万円かかることもあります。さらに、クラウド型でも注文数や出荷数に応じた従量課金制を採用しているシステムも多いです。
Q4. 既存のECサイト(Shopifyや楽天)とOMSを連携できますか?
A:はい。多くのOMSは、Shopify、楽天市場、Amazon、Yahoo!ショッピングなどの主要ECモールとの連携が可能です。OMSとECサイトを連携させることで、各販売チャネルの受注情報を自動的に統合して注文処理を一元管理できます。
Q5. OMSの導入にはどれくらいの時間がかかりますか?
A:OMSの導入期間は、選択するシステムの種類や既存の業務内容との統合範囲によって異なりますが、クラウド型であれば設定が比較的簡単なため、早ければ数日から2週間程度で導入できます。
この記事を書いた人
下川 貴一朗
証券会社、外資・内資系コンサルティングファーム、プライベート・エクイティ・ファンドを経て、2020年10月より取締役CFOとして参画。 マーケティング・営業活動強化のため新たにマーケティング部門を設立し、自ら責任者として精力的に活動している。
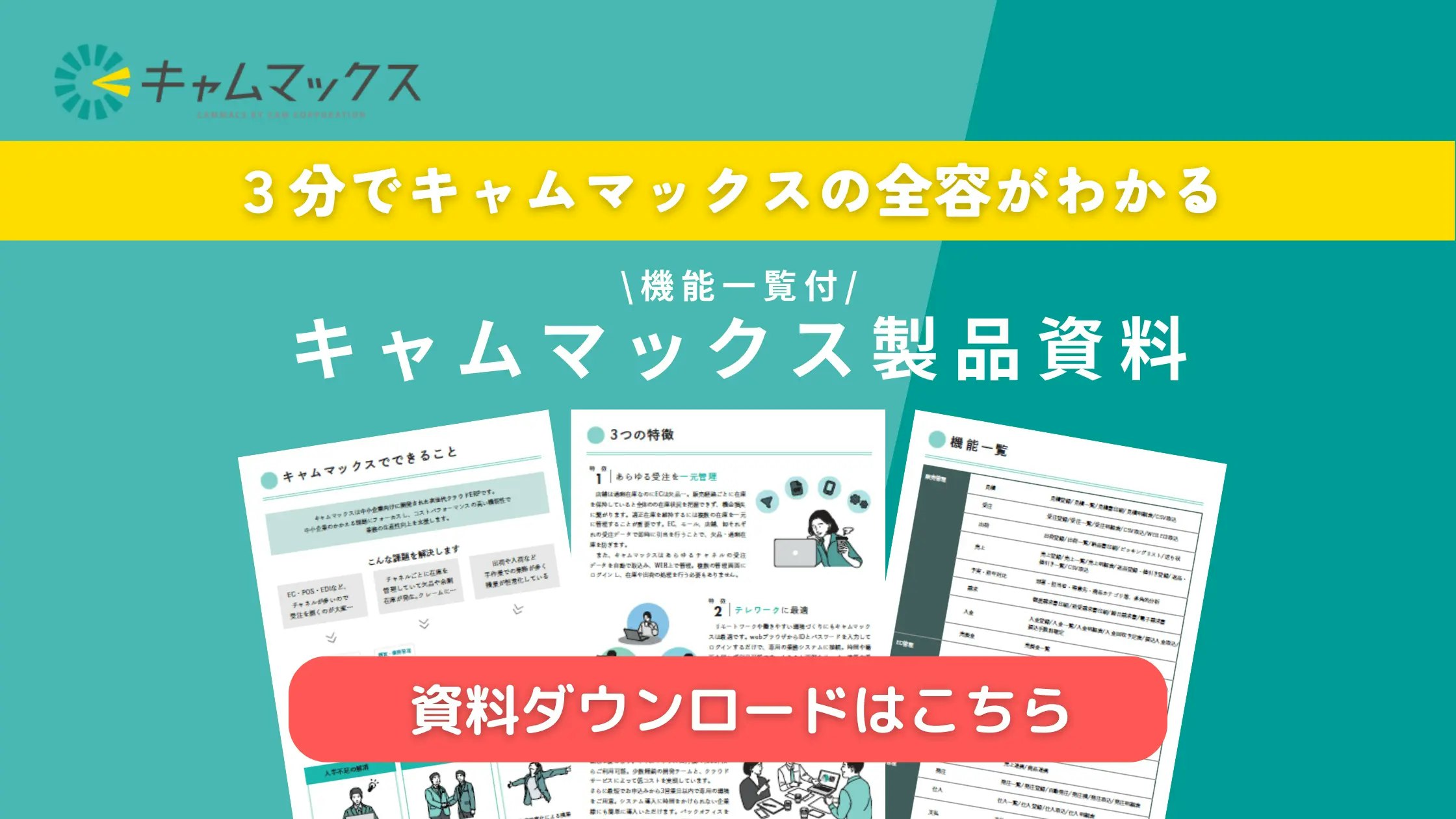



.png&w=3840&q=75)


