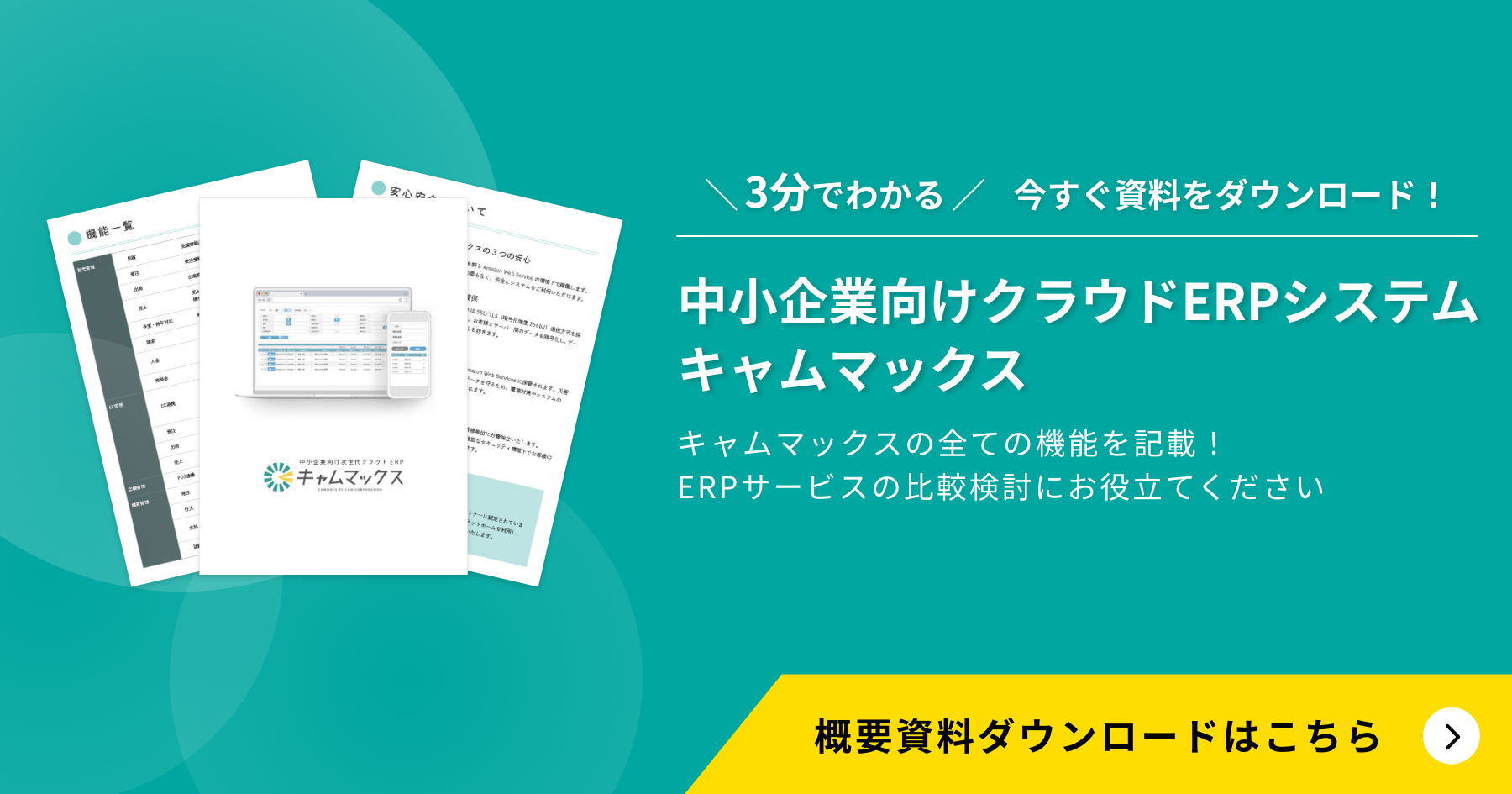クラウドシステムの基礎から活用まで|企業が知っておきたい導入ポイントを解説
クラウドシステムの活用は大企業だけの話ではなく、中小企業でも積極的に導入が進んでいます。
しかし、一方で「そもそもクラウドって何?」「メリットは聞くけど、リスクは?」「自社の業務に合うのか?」といった疑問を抱えたまま、その一歩を踏み出せない企業も少なくありません。
本記事ではクラウドシステムの導入を検討している企業担当者の方に向けて、クラウドシステムの基本から広く活用されているクラウドサービスについて詳しく解説しています。
目次
クラウドシステムとは
クラウドシステムとは、ユーザーが自らシステムやサーバーを保有することなく、インターネットを通じてITリソース(サーバー・ストレージ・ソフトウェアなど)を”必要なときに、必要な分だけ”利用できる仕組みです。
社内にサーバーを設置するオンプレミス型と比べ、導入にかかるコストの削減、柔軟な拡張性、保守や管理の負担軽減といった多くのメリットがあるため、企業のITインフラとして急速に普及しています。
クラウドベンダーの役割
ここでいう「クラウドベンダー」とは、クラウドシステムを所有・提供するプラットフォーム事業者であり、ほとんどの企業は、クラウドベンダーが所有・提供するインフラ環境などを利用して、エンドユーザーに自社のクラウドサービスを提供しています。
グローバルなクラウドベンダーにはAmazon、Microsoft、Googleなどがあり、日本国内ではNEC、NTT、GMO、富士通などが展開しています。
こうしたクラウドベンダーは、以下の役割を担っています。
- インフラ提供
サーバー、ストレージ、ネットワークなどの物理・仮想環境を設計・構築・運用
- プラットフォーム提供
OS、ミドルウェア、開発環境などを整備して開発者向けに提供
- ソフトウェア提供
業務アプリケーション、ツールの提供
- セキュリティ・バックアップ管理
データの保護、障害対応、アクセス制御など、利用者側の負担を軽減する管理体制
また、クラウドベンダーの提供するインフラを基盤としてツールを提供する「SaaS企業」も多数あります。
※SaaS(サーズ)については後ほど詳しく記述します。
クラウドの語源と意味
クラウド(Cloud)という呼び方は、インターネットで接続された先にあるサービス群を「雲」に例えたことが由来とされています。クラウドの内部構造はあたかも雲の向こう側にあり、ユーザーが仕組みを意識せずに利用できるという特性を表現しています。
この他にも、ITリソースを大量に集約して共有する考え方が「crowd(群衆)」と似ていることから、語源的に混同されて「クラウド」と定着したという説もあります。
オンプレミスとの比較
クラウドと対比される従来型の「オンプレミス」は、サーバーやネットワーク機器などのすべてを自社内に設置・管理する方式です。
それぞれの利点や特徴についてまとめます。
環境の違い
| 項目 | オンプレミス型 | クラウド型 |
|---|---|---|
| サーバー設置場所 | 自社内・データセンター | クラウドベンダーが管理するデータセンター |
| 保守・管理 | 自社で実施 | ベンダーが代行 |
| アクセス方法 | 社内ネットワーク経由 | インターネット経由 |
オンプレミスは、自社のオフィスやデータセンター内に物理的なサーバーを設置して運用・管理を行います。一方、クラウドはクラウドベンダーの設備をインターネットを介して利用するため、物理的なスペースやハードウェアの確保は不要です。
クラウドは地理的な制約を受けず、世界中どこからでもアクセス可能なことからリモートワークやグローバル展開において大きな強みになります。
導入・ランニングコストの違い
| コスト項目 | オンプレミス型 | クラウド型 |
|---|---|---|
| 初期費用 | 高額 (サーバー購入・設置費用など) | 低額(または不要) |
| ランニングコスト | 維持費・電気代・保守費が継続発生 | 月額課金・従量課金 |
| 拡張費用 | 機材追加・工事が必要 | 簡単にスペック変更・拡張が可能 |
オンプレミスでは、サーバー機器やネットワーク設備に多額の初期投資が必要となります。運用開始後も、電気代・ハード機器の維持費・保守や管理にかかる人件費などが発生します。
一方、クラウドは月額または利用した分だけ支払う従量課金など柔軟な料金体系が特徴です。
また、バージョンアップに対する対応もクラウドベンダー側の管理範囲となるため、コストを負担する必要はありません。これにより、中小企業やスタートアップ企業でもスモールスタートでシステムを開発したり導入することが可能です。
代表的なクラウドサービス
クラウドサービスが普及しはじめた2010年頃から、インターネットを介して手軽に利用できる様々なツールが提供されています。
以下、主なクラウドサービスをご紹介します。
① コミュニケーション / Web会議ツール
Web会議ツールは、遠隔地のメンバーや取引先との非対面での打合せや会議を可能にするクラウド型サービスです。リモートワークの拡大とともに、今や業務インフラとして欠かせない存在になっています。
主要なサービス
Zoom・Microsoft Teams・Google Meetなど
映像・音声・チャットによるリアルタイムコミュニケーション機能を備えており、社内外の打ち合わせや会議はもちろん、ウェビナー(オンラインセミナー)にも活用されています。
② メール・グループウェア
メール&グループウェアは、社内外との情報共有やスケジュール調整、業務管理を一元化するツールです。多拠点・多人数での業務を円滑にすることから導入している企業も多いです。
主要なサービス
Google Workspace・Microsoft 365など
メール・予定表・ドキュメントなどの共有や編集が行えます。スマートフォンやタブレット端末との親和性も高く、外出先でも手軽にアクセスできることから利便性に優れています。
③ ファイル共有・オンラインストレージ
クラウドストレージは、あらゆるファイルをオンライン上に保存・共有・同期できるサービスです。物理的なUSBメモリや社内ファイルサーバーの代替として、多くの企業で活用されています。
主要なサービス
Google ドライブ、Dropboxなど
画像やファイルをインターネット上で共有できるのはもちろん、バックアップとしても活用されています。アクセス権限の管理やログ記録など、企業での利用に適したセキュリティ機能が強化されています。
④ ビジネスチャット・タスク管理
社内外のチームメンバーとのスピーディーな情報共有や意思決定を支援するツールです。メールよりも手軽に使え、プロジェクト管理にも向いています。
主要なサービス
Slack・Chatworkなど
シンプルで直感的なUIを持ち、タスク・プロジェクト単位でのチャットが可能です。多数の企業で導入されており、社内にとどまらず取引先とのやり取りにおいても活用されています。
⑤ 基幹業務システム
従来オンプレミスで導入されていた基幹業務システムも、近年はクラウド対応が進み、手軽に導入が可能です。
さらに現在は、様々なバックオフィス業務を一元管理できるクラウドERPが普及しています。
主要なサービス
キャムマックス・アラジンオフィスなど
販売・購買・在庫・生産・会計などを一元管理できるクラウドERPで、ノンカスタマイズでも幅広い業務に対応できる点が特徴です。また、API連携にも対応しているため他ツールと組み合わせた運用も可能です。
⑥ 顧客管理・営業支援(CRM / SFA)
CRM(Customer Relationship Management)やSFA(Sales Force Automation)は、営業やマーケティングを支援するクラウドサービスです。顧客との関係を可視化・一元管理して、データ分析など通じて受注率の向上やLTV(ライフ・タイム・バリュー、顧客生涯価値)の最大化につなげることができます。
主要なサービス
Salesforce・HubSpotなど
顧客情報の管理や分析だけにとどまらず、営業管理・リード管理・予実管理なども行えます。また、名刺管理ツールなどと連携できるものもあります。
⑦ カートシステム
ECサイトの運営に必要な機能(決済・在庫管理・カートなど)を提供するクラウドサービスです。ノーコードやローコードで構築できるため、ECサイトの立ち上げや運用を手軽に行えます。
主要なサービス
Shopify、BASE、STORES、カラーミーショップなど
月額料金、または販売手数料がかかるものが一般的です。また、ECサイトだけでなく実店舗の管理と連携できるものや、グローバル展開(越境EC)に対応したものなど多種多様なサービスがあります。
⑧ 開発・インフラ関連(PaaS・IaaS)
開発者・エンジニア向けのクラウドサービスで、アプリ開発やサーバー運用のための環境をオンライン上で提供します。用途に応じて、PaaS(パース・開発環境向け)・IaaS(アイアース・インフラ向け)があります。企業は自前のサーバーを用意しなくても、クラウド上で開発・実行環境を構築できます。
主要なサービス
Amazon Web Services(AWS)、Microsoft Azureなど
世界的なIT企業が提供していることが多く、この他にもGoogleやIBM、Oracleなどが同様のクラウドサービスを展開しています。
クラウドシステムの種類
クラウドシステムは、提供される内容や利用目的に応じて「SaaS / PaaS / IaaS」という3つのサービスモデルに分類されます。
さらに、システムの提供形態によって「パブリッククラウド / プライベートクラウド」に分けられます。
SaaS
SaaS(Software as a Service)とは、ソフトウェアをインターネット経由で提供するサービス形態です。メール、会計、人事など、日常的な業務を支えるツールの多くがSaaS化されています。また、一般的に利用されているクラウドサービスの多くはSaaSに該当します。
特徴
SaaSは導入にあたってソフトのインストール作業も不要で、ユーザーアカウントの発行のみですぐに利用できる点が特徴です。ソフトウェアのバージョンアップや保守・運用もベンダー側が行うため、定期的なアップデートなども含めて常に最新のシステム環境が保たれます。
PaaS
PaaS(Platform as a Service)は、アプリケーション開発に必要な開発環境やフレームワークをクラウド上で提供するサービスです。エンジニアはOSやサーバーの構築を意識することなく、開発・テスト・本番運用までを一貫して行えます。
代表サービス:AWS Lambda、Azure App Service、Google App Engineなど
特徴
PaaSはインフラ構築の手間を省き、アプリ開発に専念できるのが特徴です。スケーラビリティにも優れており、トラフィック増加に応じて自動的にリソースを調整できるため、安定した運用が可能です。
IaaS
IaaS(Infrastructure as a Service)は、仮想サーバーやネットワーク、ストレージといったITインフラをクラウドで提供するモデルです。OSの選定・設定、アプリケーションのインストールなど、システムの設計・開発を自由に行える点が特徴です。
代表サービス:Amazon EC2、Microsoft Virtual Machineなど
特徴
柔軟性とカスタマイズ性が最も高く、開発から商用環境までスケールしやすい特徴があります。一方で、OSやミドルウェアの管理、セキュリティの設定などもユーザー側の責任となるものが多く(責任共有モデル)、従来のオンプレミス環境に近い運用となります。
プライベートクラウドとパブリッククラウドの違い
| 比較項目 | パブリッククラウド | プライベートクラウド |
|---|---|---|
| 利用者 | 複数の企業で共有 | 特定の1社専用 |
| 導入コスト | 低コスト | 高コスト |
| カスタマイズ性 | 標準的な機能に限定 | より自由度が高く、自社要件に最適化可能 |
| セキュリティ・制御 | 標準化されたセキュリティ設定 | 自社のポリシーに沿った設定が可能 |
2つの違いは、クラウド上にあるサーバーの共有範囲やアクセス環境にあります。
パブリッククラウドは複数のユーザーで共有するクラウド環境であることに対して、プライベートクラウドは特定の企業や組織が専用に構築したクラウド環境になります。
プライベートクラウドが必要とされる理由
プライベートクラウドが求められる背景には、企業や組織が扱う機密性の高い情報や法規制の厳しい業務の存在があります。特に金融・医療・官公庁などでは、他社と環境を共有するパブリッククラウドでは対応しきれないケースが多く見られます。
例えば、金融機関では、口座情報や取引履歴といったセンシティブな情報を日常的に扱い、金融情報システムセンター(FISC)や金融庁による厳格なガイドラインへの対応も求められます。こうした背景から、物理的に分離され、自社で細かく制御できるプライベートクラウドの採用が進んでいます。
同様に医療機関では、診療記録や検査データなどの特定個人情報の厳格な管理が求められる事から専用のクラウド環境が有効とされ、大学病院などを中心に導入が広がっています。
官公庁・自治体・研究機関でも行政文書や未公開データを取り扱うため、情報漏えいリスクを最小限に抑える手段として一部をプライベートクラウドにて運用しており、政府主導のガバメントクラウドもこの考え方に基づいて運用されています。
クラウドシステムが注目される背景
働き方改革・リモートワークの加速
2019年の「働き方改革関連法」に加え、2020年以降のパンデミックを契機に、日本でもリモートワークの普及が急速に進んでいます。この変化の中で、オンプレミス型システムは社外からのアクセス制限やハードウェア依存といった課題が顕在化しました。一方、クラウドシステムはインターネット環境さえあれば場所を問わず業務が可能なためリモートワークとの高い親和性が評価されています。
災害時におけるBCP対策
日本は地震・台風・洪水など自然災害が多く、BCP(事業継続計画)対策の重要性が年々高まっています。「万が一のときにも業務を止めない仕組みづくり」が求められる中、クラウドシステムは物理設備に依存せず、災害時でも他拠点から業務を継続できる柔軟な体制づくりを実現します。BCPは経営サイドから現場まで共通の課題であり、クラウド活用はその実効性を高める有力な手段と言えるでしょう。
クラウドシステムのメリット
コスト面での優位性
従来のオンプレミス型は、ハードウェア購入費、環境設備費などが高額になる傾向があり、導入判断に大きなハードルがありました。対してクラウドはインフラを保有せずに利用できるため、初期投資を抑えてスタートすることが可能です。これにより、中小企業や新規事業部門でも、資金面のリスクを最小限にしながら導入を進めることができます。
利用環境の柔軟性
インターネット接続さえあればシステムを利用できることから、オフィスはもちろん、在宅勤務や出張先、海外拠点など、業務の場がどこであっても同一の業務環境を再現できます。これは現代の働き方において極めて重要と言えるでしょう。また、PC・スマートフォン・タブレット端末で利用できるため、業務内容に応じて最適な機器を選択できる柔軟性を持ち合わせています。
拡張性とAPI連携
クラウドサービスの多くは、事業の成長や変化に応じてシステムを拡張しやすいという点も魅力です。例えば、新たな機能を追加したり、データ量の増加に応じてプランを変更したりと、規模に合わせてスムーズに拡張・縮小することが可能です。また、APIを利用して外部ツールと連携できるなどビジネスニーズに応じた使い方が可能です。
業務効率化と生産性向上
クラウドシステムの導入により、部門間でリアルタイムに情報を閲覧・共有できることからコミュニケーションのロスを防ぎ、意思決定のスピードが向上します。さらに、ビジネスチャットやファイル共有、タスク管理などにより日常業務の効率化が進みます。結果として従業員一人ひとりの生産性が底上げされ、組織全体としてのパフォーマンス向上につながります。
クラウドシステムのデメリットと注意点
自社業務との適合性とカスタマイズ制限
クラウドシステムはパッケージ型のものが多く、個別の業務に合わせた柔軟なカスタマイズが難しい場合があります。そのため、システムに合わせて業務フローを見直す必要が出てくる場合もあります。導入前に「どの業務をクラウド化するか」「どの業務を既存システムのまま残すか」といった視点からシステムの導入やリプレイスを検討しましょう。
セキュリティや障害のリスク
クラウドはインターネットを介して外部ベンダーのインフラを利用するため、利用者がセキュリティに対して高い意識と対策をしておかなければ、情報漏洩や不正アクセス、サービス停止といったリスクが常に存在します。特に個人情報や財務情報など機密性の高いデータを扱う場合には、クラウドへの保存や処理に対する懸念がまだまだ根強くあります。また、ベンダー側で発生した障害によりユーザー企業の業務に影響が及ぶこともリスクとして挙げられます。
まとめ
中小企業においては、資金や人材といったリソースが限られている一方で、事業スピードや変化対応力が競争力を左右する重要な要素となる場面が多く見られます。その中で、クラウドシステムは少ないリスクで大きな効果を狙える非常に有効な成長戦略の一つです。
初期投資を抑えたスモールスタートが可能であり、必要な機能だけを段階的に導入できる点は中小企業にとって大きな魅力です。
実店舗からECサイトまで!おすすめのクラウドサービスはキャムマックス

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象企業 | 中小企業(特に製造業、小売業、卸売業など) |
| 対応業務 | 販売・購買・生産・在庫・財務会計までを一元管理 |
| チャネル対応 | EC・店舗・卸のオムニチャネルに対応 |
| カスタマイズ性 | ノンカスタマイズでも幅広い業務にフィット |
| 費用 | 月額9万円〜、保守サポート込み |
これまで「ERPは大企業のもの」という印象が強くありました。しかし、業務効率化や経営の可視化を目指す上で、中小企業こそクラウドERPの導入が不可欠です。
キャムマックスでは在庫・販売・購買・生産・財務会計と幅広い基幹業務をクラウド上で一元管理します。各部門の業務を一つのシステムでつなぐことで、情報の分断を防ぎ、入力作業の手間やミスを削減でき、さらにリアルタイムでの在庫・売上・利益の把握が可能となるため経営判断のスピードと精度が飛躍的に向上します。
初期費用10万円・月額9万円から、最短3営業日で環境構築
クラウドサービスのため初期コストやランニングコストを抑えられ、申し込みから3営業日で試用環境をご提供できます。さらに、60日間の無料トライアルも設けており、導入前にしっかりと操作性や機能をお試しいただけます。
期間中はサポート担当がつきますので、導入前に操作性の確認や利用方法など十分にご確認頂くことが可能です。
この記事を書いた人
下川 貴一朗
証券会社、外資・内資系コンサルティングファーム、プライベート・エクイティ・ファンドを経て、2020年10月より取締役CFOとして参画。 マーケティング・営業活動強化のため新たにマーケティング部門を設立し、自ら責任者として精力的に活動している。