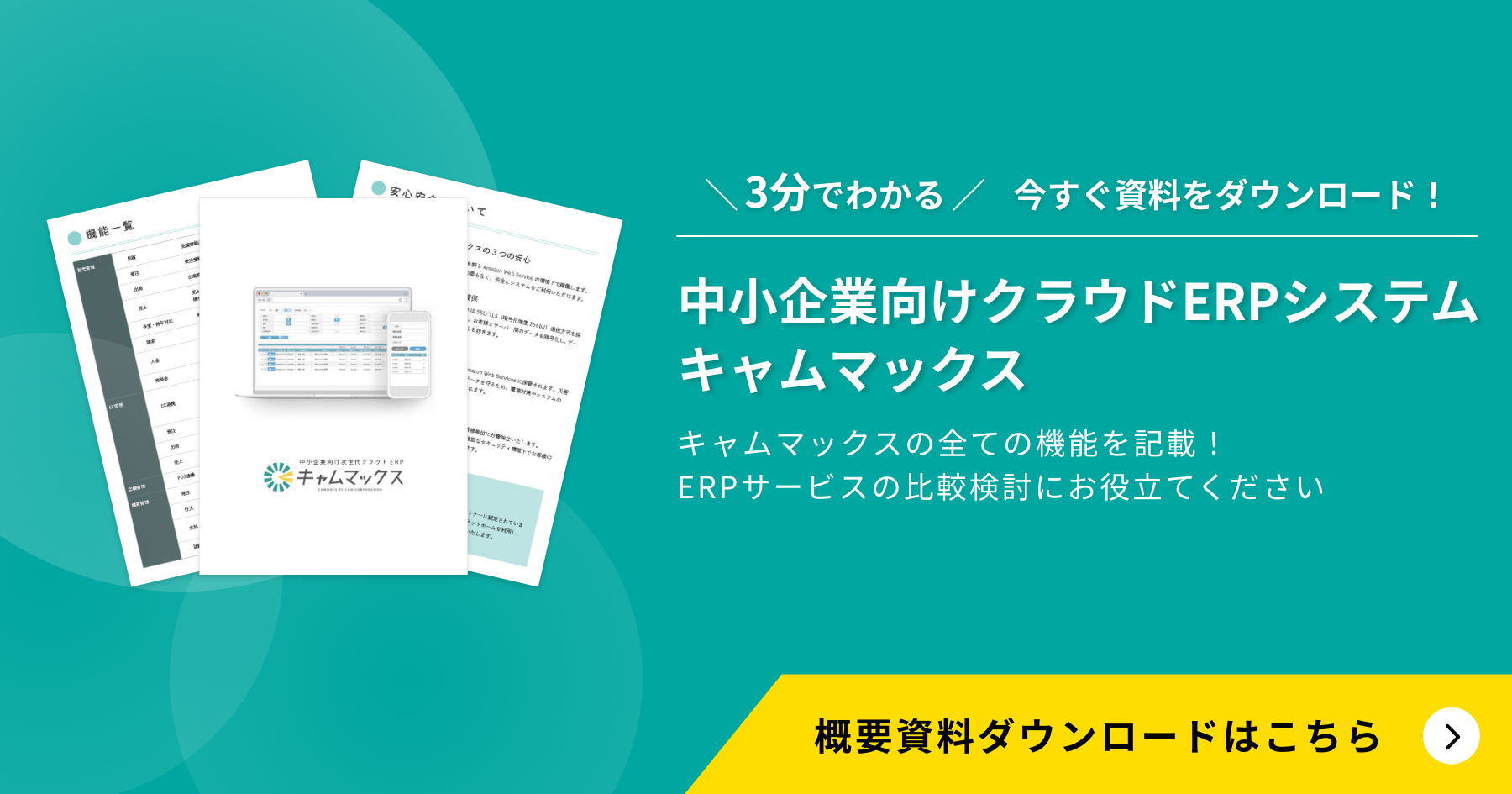店舗の在庫管理はシステムで効率化!在庫管理の課題と解決策をまとめて解説
飲食店やアパレル業界において『在庫管理』は、経営の利益率に直結する重要な業務です。しかしながら、過剰在庫や在庫不足、食品ロス、流行の変化への対応といった複雑な課題に対して、多くの経営者が適切な解決策を模索しているのが現状です。
本記事では、在庫管理における具体的な課題を整理して、それらを解決するための方法を解説。飲食店舗やアパレル店舗特有の事情に応じた具体的な施策についても取り上げています。食品ロスや店舗在庫の過不足に悩む方はぜひ、最後までお読みください。
目次
店舗の在庫管理における課題
インターネット経由の取引が急増している昨今において、スピーディーに在庫を取り寄せることができるようになった反面、従来のアナログ的な在庫管理方法による問題点が浮き彫りになっています。店舗の在庫管理における主な課題を挙げてみます。
在庫過剰や在庫不足の問題
店舗ではできるだけ多くのお客様に商品を購入してもらいたいという気持ちから大量に在庫を持ってしまうことがあります。
しかし、実際には思ったほど売れなかった場合など、いつまで経っても在庫が減らないという問題が発生します。その結果、仕入れに対して利益が得られないことに加え、新たな在庫を受け入れるスペースを圧迫するということになります。
逆に、過剰在庫を防ごうと仕入れを抑制してしまうと、せっかく欲しいという人がいるのに販売ができないという機会損失の問題も発生してしまいます。
適量な在庫数を求める計算は、過去のデータを参照することから成り立っていることが多いですが、これからの時代は様々なツールを活用し、ある程度未来の需要予測を読める対策が必要になってきます。
在庫の正確性の問題
先ほどの在庫過剰や在庫不足の問題は、在庫数が正確であるという前提であっても生じる問題です。
しかし、店舗によっては人が手作業で数え間違いや、紛失したものを含めていなかったりとずさんな在庫管理が行われていることで、実際の在庫数がデータと一致しないという問題も多いです。特に急成長を遂げた店舗などは、手動での管理体制では追いつかなくなっていまいミスも多くなってしまいます。
在庫の追跡の問題
在庫があると言っても、店舗に置いてあるのか物理的に離れた倉庫にあるのかによっても扱いが異なります。手動で在庫管理を行っている場合は、在庫を倉庫からトラックなどで運ぶ際、今在庫がどこにあっていつ届くのかといった詳細なデータを確認できず、届いたのかどうかもわからないということになりかねません。
飲食店舗における在庫管理特有の課題
飲食店舗の場合は他の商品を扱う店舗と異なり、在庫管理にも特別な配慮が必要となります。飲食店舗の在庫管理の大きな課題は以下になります。
消費期限や賞味期限の問題
飲食店舗では、食材を保管する際に消費期限や賞味期限に注意しなければならないという難しい問題があります。
これらの期限をしっかり管理できていないと、飲食店舗にとっては致命的なダメージを負うことになってしまうでしょう。
在庫保管環境の問題
飲食店舗の食材は、常温だけでなく冷蔵や冷凍という保管方法が必要になります。
しかも、同じ冷蔵でも食材によっては適温が異なるというケースがあり、飲食店舗ではこれらの保管環境も管理しなければなりません。
飲食店舗の在庫管理における課題を解決する方法
上記のように、飲食店舗には他の店舗とは異なる課題がありますが、これらの課題を解決するための具体策をご紹介致します。
品質管理の徹底
消費期限や賞味期限を過ぎることが無いように、定期的な棚卸で数量とともに期日を確認することが必要となります。
また、食品の品質管理に取り入れたいのがロット管理です。商品を一つ一つ管理していると、先に入荷したものと後から入荷したものが混ざってしまいます。
しかし、ロット管理なら入荷ごとにグループ化して先に来た在庫から使用することができます。
さらに、ロット管理は食材のトレーサビリティを実現することもできます。どこで製造され、どこからどのように送られてきたのかわかるようになっています。
もし、その食材を製造した工場で品質に問題があることがわかった場合、ロット番号から問題の商品だけを簡単に取り除くことが可能になります。
需要予測を行う
飲食店舗に限らず、発注の際に今後どれくらいの需要が見込まれるのか予測することは大切です。
飲食店舗の場合、経営者や店長などが長年の勘で発注量を決めているということも少なくありませんが、食品ロスも問題視されている中、本格的に取り組む必要があるでしょう。
在庫管理の標準化・マニュアル化
飲食店舗での在庫管理では食材の品質管理も重要となることから、発注のタイミングなども含めた決まりを細かく設定する必要があります。
できるだけ従業員全員の協力をはかるためにも、その内容を標準化やマニュアル化しましょう。
IoTを活用してフードロスを削減
IoT(Internet of Things)技術を利用することで、店舗の在庫管理をより効率的で正確に行うことができます。たとえば、在庫の利用状況をリアルタイムでトラッキングし、必要に応じて自動的に発注することができるのです。これにより、在庫の過剰を防ぎ食品のロスを減らすことができます。さらに、データ収集と分析が簡単に行え、より正確な需要予測と在庫管理が可能になります。
アパレル店舗における在庫管理特有の課題
小売店舗の中でも飲食店舗に次いで特殊な事情があるのがアパレル店舗です。どのような課題があるかをご紹介致します。
豊富なサイズやデザイン
アパレル店舗の場合、デザインの豊富さはもちろんのこと、お客様のサイズが一定ではないため、ある程度サイズのバリエーションが求められます。そのため、同じデザインに対して確保しなければならない在庫が多くなるのが特徴です。
流行や季節変動
日本の場合は四季に応じて着るものが変わるという特性があるため、アパレル店舗ではシーズンごとの需要を見極めなければなりません。毎年流行が変わるため、同じ季節でも前年の在庫は使うことができないのです。
店舗DXで課題を解決!在庫管理システムを導入するメリット
このように、アパレル店舗では大量の在庫を確保しておく必要がありますが、こうした管理の問題を解決するには以下のような方法が考えられます。
在庫管理の標準化・マニュアル化
流行や季節により発注する在庫が大きく変動するアパレル店舗では、どれだけ実際の販売量との乖離を防ぐかが重要なポイントとなります。
店長の勘に頼っているのでは難しいため、属人化を防ぐためにも在庫管理方法をマニュアル化して、誰もが明確な根拠で行うことができるようにしなければならないでしょう。
RFIDの導入
RFID(Radio Frequency IDentifier)は、電波を使って読み取ることのできる電子タグを使ったシステムです。
これまでもアパレル店舗の在庫管理ではバーコードが活用されてきましたが、この場合は入荷した大量の在庫を一つ一つ読み込むといった作業が必要でした。
その点RFIDは電波で一度に読み込むことができるため、在庫管理の時間が大幅に削減できるのが特徴です。
店舗の在庫管理にシステムを取り入れるメリット
| 項目 | 従来の在庫管理方法 | 在庫管理システム導入後 |
|---|---|---|
| 作業効率 | 手作業が中心で時間がかかる | 自動化により作業時間が大幅に短縮 |
| データの正確性 | ヒューマンエラーが発生しやすい | リアルタイム更新でデータの正確性が向上 |
| 在庫追跡 | 手動での記録で追跡が難しい | 入出庫や現在の在庫状況を簡単に確認可能 |
| コスト削減効果 | 過剰在庫や機会損失が多発 | 適正在庫を維持して無駄なコストを削減 |
| 需要予測 | 経験や勘に依存した発注 | 過去データを基にした正確な需要予測 |
| 導入費用 | 特別な初期費用は不要 | システム費用が発生(長期的にはコスト削減) |
飲食店舗やアパレル店舗の例からもわかるように、在庫管理を手動で行うのは限界があります。店舗の在庫管理の課題は在庫管理システムやERPシステム、スマホでアプリを導入することで一気に解決する可能性が高いです。
在庫の追跡と管理が容易
システムによって在庫数の把握ができ、商品の仕入れや発注の管理が自動化されるため、従来の手作業に比べて作業時間が短縮されます。
また、入荷・出荷に関する手違いや在庫の過不足などに関する人為的ミスも減少します。
在庫コストの削減
在庫管理システムによって在庫数や発注量を最適化できるため、在庫コストの削減が期待できます。
必要最低限の在庫量を維持することで、不必要な在庫を抱えることを避けることができます。
需要予測がしやすい
在庫システムによっては需要予測機能がついているものがありますし、機能として存在しなくても日々の在庫データが蓄積されることで予測がしやすくなるというメリットがあります。
小売業が在庫管理システムを導入する理由|EC拡大と市場競争の対応策
小売業界では、市場の変化に素早く適応し効率的な運営を実現するために、在庫管理システムの採用が急速に進んでいます。
特に、EC市場の拡大がこの傾向に強く影響しています。
市場の変化への迅速な対応
小売業界は常に変化しており、消費者の購買行動やトレンドに迅速に対応する必要があります。
そこで在庫管理システムを導入することで、リアルタイムで在庫状況を把握し市場の変化に合わせて商品の発注や在庫調整を行うことができます。
これにより、従来のアナログ管理では処理に時間がかかり、ミスも多く発生していた業務から解放され、在庫過剰や不足を防ぎ販売機会を最大限に創出することが可能です。
ECの成長とオムニチャネル戦略
近年、EC市場の成長が顕著で、多くの消費者がオンラインでのショッピングを利用しています。
そのため、多くの企業が複数の販売チャネルを持ち、顧客への販売機会を逃さないようにする動きが活発化しております。
このようなオムニチャネル戦略の中で、小売業者はオンラインとオフラインの在庫を統合的に管理する必要になってきています。
そこで在庫管理システムを導入することで、異なる販売チャネルの在庫を効率的に管理することができます。
競争激化と顧客要求の高まり
小売業界は競争が激化しており、顧客はスピーディーな購入体験を常に求めています。
在庫管理システムを活用することで、店舗は正確で確実な商品提供を行うだけでなく、商品の在庫切れを防ぎ販売機会の損失を軽減する必要があります。
こうしたサービス品質の向上が、顧客の信頼性を高め売上の拡大につながります。
在庫管理システムの主な機能
入出庫管理機能
入出庫管理機能は、商品の在庫状況をリアルタイムで把握し、管理できる重要な機能の一つです。
具体的には商品の入庫、出庫、移動などの在庫変動を正確に記録し常に最新の在庫情報を保つことができるので、在庫過多や不足を防ぎ、適切な在庫量を維持できます。
また、商品のロット番号や賞味期限などの詳細情報も管理でき、商品の追跡や品質管理が向上します。
検品機能
検品機能とは、商品が倉庫に入庫する際や出荷前に数量と品質を確認し、正確な商品が適切な数量で取り扱われていることが確認できる機能です。
主にハンディターミナルなどの端末と連携して活用され、商品のバーコードを読み取るだけで品目や数量が合っているかをシステム側で確認することができるので、伝票の内容との一致しない場合はシステムが再度確認を行うよう指示されます。
これにより、誤った出荷や在庫の誤差を防ぐことができます。
返品管理機能
返品管理機能とは、顧客からの返品や不良品の処理をスムーズに行い、在庫情報を正確にアップデートするための機能です。
返品処理のスピードを上げるとともに、返品に関する詳細な情報を記録し、将来の品質向上や返品防止策の策定に役立てることができます。
また、返品による在庫の変動を正確に反映させることで、在庫数の正確性を維持しより高い在庫管理が可能になります。
棚卸機能
棚卸機能とは、在庫管理システムにおいて在庫の正確性を保つために不可欠な機能であり、データと実際の在庫の数量に間違いがないかを確認することができる機能です。
物理的な在庫とシステム上の在庫情報を照らし合わせ、不一致があればそれを修正することが可能となり、検品と同様にバーコードを利用して管理することで、目視によるミスを防ぎながら正確な数を容易に入力することができます。
在庫分析機能
在庫分析機能とは、見落とされがちな売れ筋商品や滞留在庫商品を把握し、過去の出荷データと現在の在庫状況を基に、次回の仕入れ時期と数量を見積もることが可能になる機能です。
この機能を利用することで、在庫の動向を追跡し在庫の過剰や不足の原因を特定でき、商品の販売トレンドや季節の変化を分析することで、需要予測の精度を向上させることができます。
データ抽出機能
データ抽出機能とは、在庫管理システムに蓄積された大量のデータから、必要な情報を効率的に抽出するための機能です。
この機能を利用することで、特定の条件に基づいてデータを抽出し、レポートや分析のために利用することができます。
これにより、ビジネスの意思決定を迅速かつ正確に行うことが可能となり、全体的な運営の効率化を実現することができます。
マスタ管理機能
マスタ管理機能は、商品、取引先、社員、顧客などの基本情報を統一的に管理し、データの一貫性と正確性を確保するための機能です。
この機能を活用することで、在庫の種類や製品の収納場所・取引先情報・システム利用者などの情報を一括管理できます。
これにより、新しい商品や取引先を追加する手続きを効率化し、データ管理をスムーズに行うことが可能です。
店舗向けおすすめ在庫管理システム・アプリ
キャムマックス

『キャムマックス』は在庫管理だけでなく、販売管理や購買管理、財務会計までも可能な多機能なクラウドERPシステムです。
在庫管理機能については、リアルタイムで発注や入出荷の管理を一元化することができ、業務の効率化が図れます。
また、売上分析や取引先・仕入先の管理も行えるため、バックオフィス業務をスマート化できます。
zaico

『zaico』は、在庫の最適化を図り過剰在庫や品切れを防ぐことで、コスト削減と効率的な在庫管理を実現できるクラウド在庫管理システムで、PCやスマートフォンからアクセス可能です。
バーコードスキャン機能を利用して簡単に商品情報を登録でき、在庫の入出荷もリアルタイムで把握することができます。
また、複数の拠点での在庫管理もサポートしており、ビジネスの拡大に合わせて利用範囲を広げることが可能です。
Tana

『Tana』は、シンプルな操作性と直感的なインターフェースで初心者でも簡単に使いこなすことができ、スマートフォンだけで全ての機能を利用できる在庫管理アプリです。
特に少量多種の資材が消費される環境での在庫管理に適しており、チームでの共同管理も可能です。
バーコードスキャン機能やクラウドデータ保管も備えており、在庫管理を効率的に行うことができます。
eeeCLOUD

『eeeCLOUD』は、企業向けの在庫管理システムで在庫の適正化を図り、過剰在庫や品切れを防ぐことでコスト削減と効率的な在庫管理を実現できる管理ツールです。
在庫のリアルタイムな把握や分析機能を備えており、ビジネスの意思決定を効果的にサポートします。
ユビレジ在庫管理
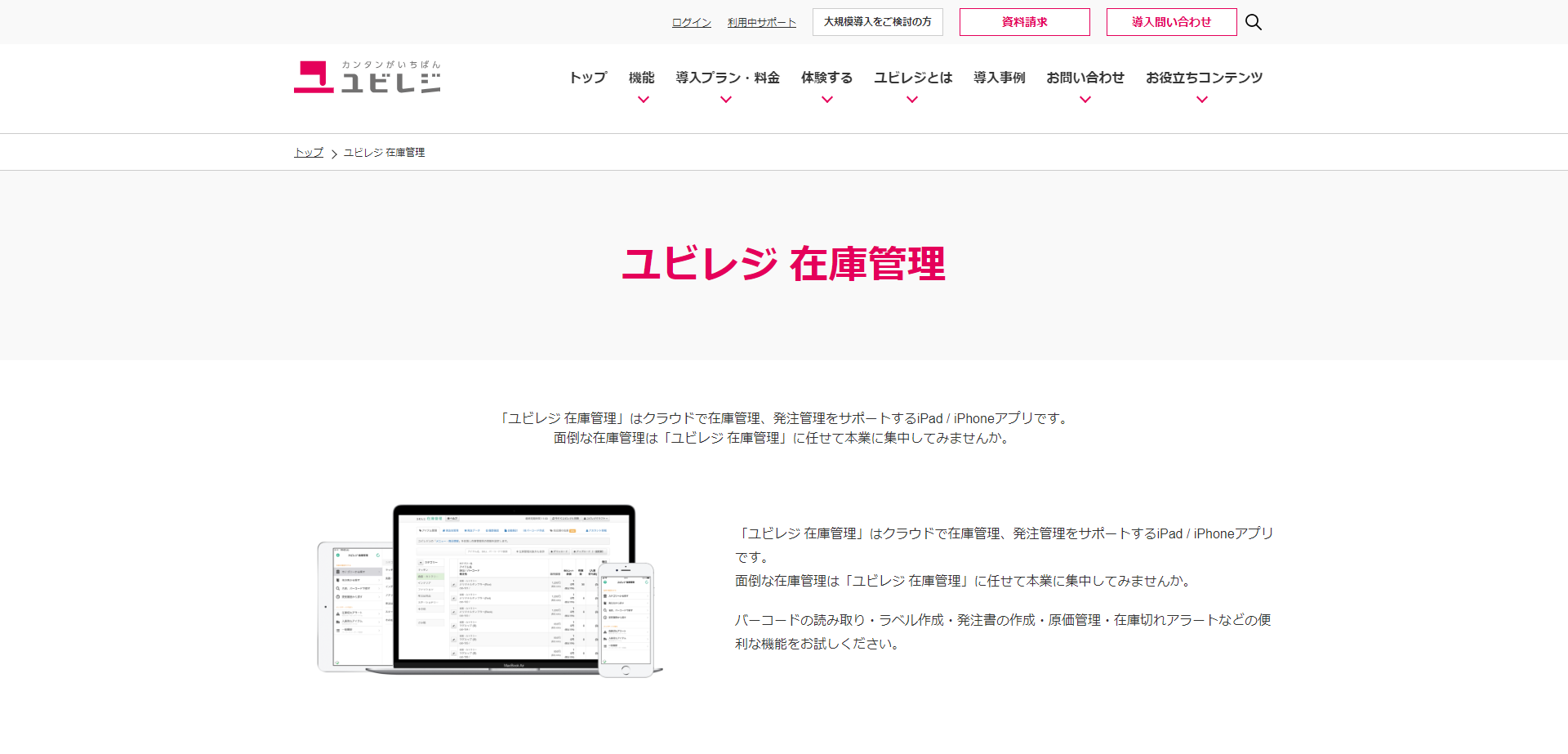
『ユビレジ在庫管理』は、店舗運営をスムーズにし在庫管理の効率化を図ることができ、iPadやiPhoneを利用してクラウド上で在庫管理や発注管理をサポートするアプリです。
バーコードの読み取りやラベル作成、発注書の作成など、便利な機能が豊富に用意されています。
また、30日間の無料トライアルも提供されています。
ロジクラ

『ロジクラ』は、物流業界に特化した在庫管理システムで、物流業界特有のニーズに応えるための機能が豊富に用意されており、業務の効率化と在庫管理の精度向上を実現できるツールです。
倉庫内の在庫状況をリアルタイムで把握し、効率的な在庫管理をサポートします。
また、在庫の最適化を図ることで過剰在庫や品切れを防ぎ、コスト削減に貢献します。
キャムマックスはアパレルや飲食など店舗の在庫管理が可能
キャムマックスは、中小企業向けに開発されたERP(基幹業務)システムで、具体的な機能には販売・債権管理、購買・債務管理、在庫・倉庫管理、財務会計が含まれます。
キャムマックスの在庫管理機能では、飲食店舗に必須の期限管理も可能であることに加え、WMSと連携して倉庫の管理も可能です。
ECサイトを含む複数チャネルでの店舗運営で特に複雑になりがちな在庫管理にお困りの企業様は、ぜひ一度ご相談ください。
FAQ(よくある質問)
Q1. 在庫管理システムを導入するメリットは何ですか?
A:在庫管理システムを導入することで店舗運営が効率化されます。バーコードリーダーなどを併用すれば、手動で行っていた在庫の入出庫作業の正確性も向上するため、作業時間が短縮するだけでなくヒューマンエラーの削減にも繋がります。
Q2. 飲食店舗の在庫管理で特に注意すべき点は何ですか?
A:飲食店舗では、消費期限や賞味期限の管理が特に重要です。期限切れの食材の利用を防ぐため定期的に棚卸を行い、ロット管理を活用して古い在庫から優先的に使用する仕組みを整える必要があります。また、食材ごとに適切な温度で保管することも大切ですので、どの倉庫に何を保管しているのかを常に把握しておく必要があります。
Q3. 在庫管理システムはどの業界でも活用できますか?
A:在庫管理システムは、ほぼすべての業界で活用できますが、特に飲食業界やアパレル業界は効果的です。
飲食業界では食品の品質管理やロス削減、アパレル業界では多品種小ロットの在庫の一元管理に利用されています。
Q4. 在庫管理システムの主な機能は何ですか?
A:在庫管理システムには、入出庫管理・棚卸・返品管理などの機能があります。入出庫管理では在庫の増減をリアルタイムで記録できるので、常に在庫状況を把握できます。また棚卸機能では、実際の在庫とシステム上のデータを照合して在庫の正確性を保ちます。
Q5. IoT技術を活用した在庫管理とは何ですか?
A:IoT技術を活用することで在庫管理がさらに効率化されます。例えば、IoT技術に代表される「重量センサー」や「RFIDタグ」を使って倉庫内にある大量の在庫を瞬時に計測することも可能です。
Q6. 在庫管理システムを導入する際の費用はどれくらいですか?
A:在庫管理システムの費用は、導入規模や機能の充実度によって異なります。小規模店舗向けのクラウド型システムは、月額数千円から数万円で利用可能です。一方、大企業向けのERP(基幹システム)の場合、初期費用が数十万円から数百万円に及ぶことがあります。システムの選定時には、事業の規模や予算に応じた製品を選ぶことが重要です。
Q7. 小売業界で在庫管理システムが求められる理由は?
A:小売業界では、EC市場の成長に伴い、オンラインとオフラインの在庫を一元管理する必要性が高まっています。在庫管理システムを導入することでオムニチャネルに対応した在庫管理が可能になります。こうした市場の変化に迅速に対応することで、販売機会を逃さず競争の激しい市場で優位性を保つことができます。
この記事を書いた人
下川 貴一朗
証券会社、外資・内資系コンサルティングファーム、プライベート・エクイティ・ファンドを経て、2020年10月より取締役CFOとして参画。 マーケティング・営業活動強化のため新たにマーケティング部門を設立し、自ら責任者として精力的に活動している。